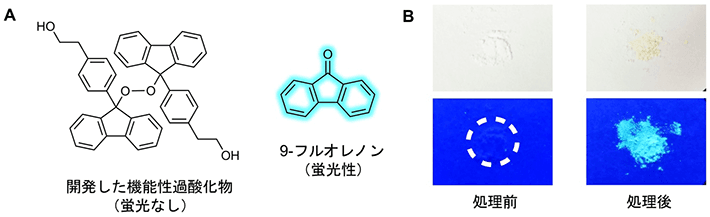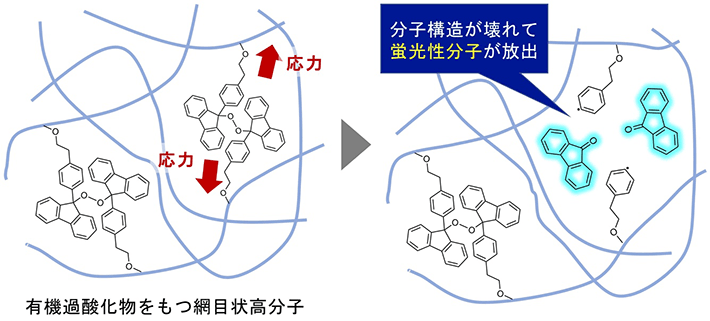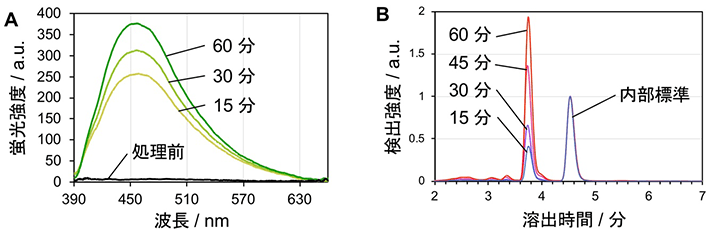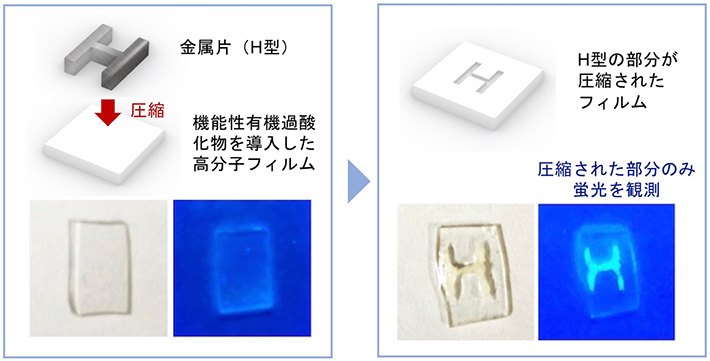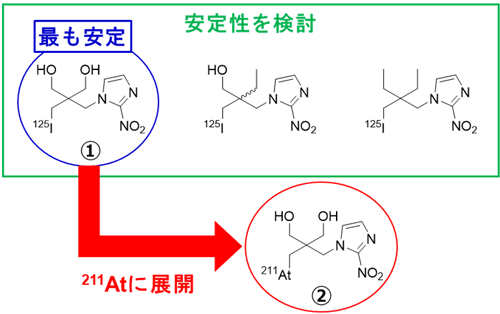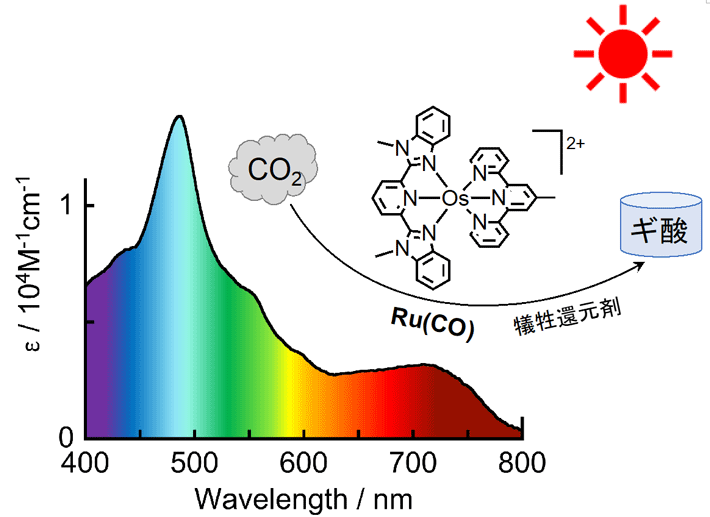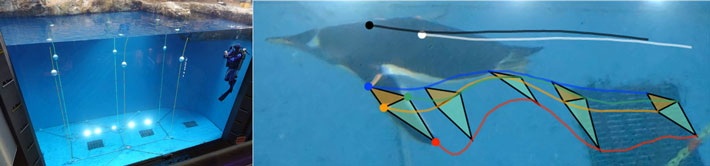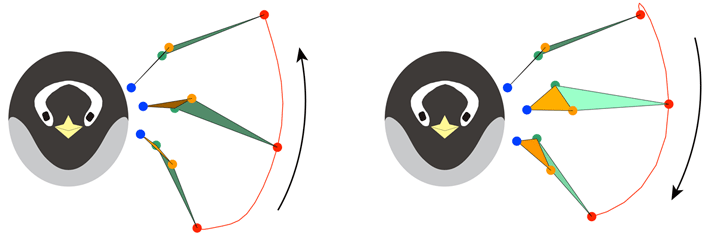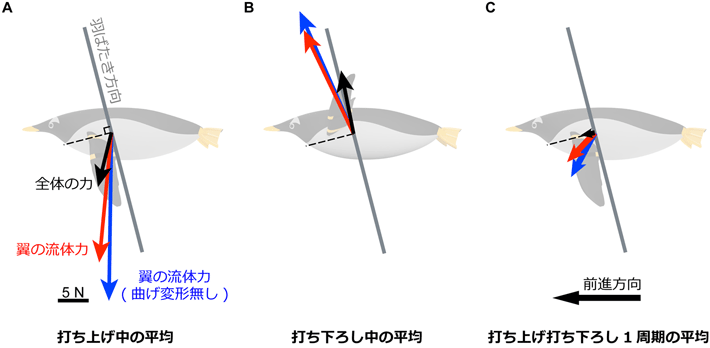要点
-
LaTiO3に人工的に圧力を加え、絶縁体から金属状態へ変化させることで、高性能な熱電変換材料を開発
-
電気伝導率と熱起電力の両方を同時に増加させ、熱電変換出力が2桁増大
-
従来の理論を超えて熱電性能を大きく向上させる新技術として期待
概要
東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所の片瀬貴義准教授、神谷利夫教授、元素戦略研究センターの細野秀雄栄誉教授らの研究グループは、熱から電気を取り出す熱電変換[用語1]材料の性能を高める妨げになっている、電気伝導率と熱起電力のトレードオフ状態を解消させる技術を開発し、熱電変換出力因子[用語2]を2桁増大させることに成功した。
廃熱として捨てられることの多い熱エネルギーの有効活用に向け、効率の良い熱電変換を行うには、電気を通しやすい性質を持ち、温度差を与えた時により大きな電圧を発生させる性質を兼ね備えた熱電材料が必要になる。しかし前者の「電気伝導性の高さ」と後者の「電圧=熱起電力の大きさ」にはトレードオフの相関があり、熱電材料の性能を向上させる限界となっていた。
本研究では、モット絶縁体[用語3]の酸化物であるLaTiO3に人工的に圧力を加え、絶縁体から金属に変化させると、この2つが両立することを発見した。同物質に圧力を加えると、電荷の移動を担うキャリア[用語4]の濃度であるキャリア濃度[用語5]が減少して熱起電力が大きくなると同時に、キャリア濃度が減る以上にキャリア移動度[用語6]が大幅に高まることで電気伝導性も増大するため、トレードオフの関係を破ることが明らかになった。
この発見は化学的に安定な酸化物の熱電性能を大きく向上させる新しい指針に繋がり、今後、熱電変換が汎用的なエネルギー源として普及することが期待される。
研究成果は「Advanced Science」誌に10月21日付(現地時間)で掲載された。
背景
近年、先進国では、消費されているエネルギーのうち約6割が未利用のまま廃熱として捨てられている。このような廃熱を電気エネルギーとして回収し、再利用することを可能にする熱電変換は、温暖化の抑制や省エネに寄与する技術として注目を集めている。
これまで変換性能の高い熱電材料としては、ビスマス・テルル化合物などの金属カルコゲン化物が知られてきたが、毒性元素を含む点や熱的・化学的な安定性に問題があり、大規模な社会利用への障害になっている。一方、酸化物は高温・空気中においても安定であることから、メンテナンスフリーの熱電変換素子への応用が期待されるが、金属カルコゲン化物と比べて、熱電変換性能が低いという問題があった。
熱電変換では、電気を通す金属などの導体、あるいは半導体といった熱電材料に温度差を与えることで材料内に電位差、つまり熱起電力としての電圧を発生させて熱を電気に直接変換する(図1左)。熱電変換で得られる電気出力は、温度差によってどれだけの熱起電力=電圧が得られるかを表す指標である「ゼーベック係数:S」の2乗と、「電気伝導率:σ」との積である出力因子「S2×σ」で表される。つまり、熱電材料の「ゼーベック係数:S」を大きく、かつ、「電気伝導率:σ」を高くすることができれば、電気出力は大きくなる。
熱電変換材料のSとσはキャリア濃度に依存するため、これまで、不純物を添加してキャリア濃度を調整し、出力因子を最大化させる方法が一般的にとられている(図1右)。しかし、熱電材料に関する従来の簡単な理論モデルでは、キャリア濃度を増やしてσを高くするとSが小さくなる「トレードオフの関係」が存在するため、大きなSと高いσを両立させることはできず、大きく性能を上げることができないという問題を抱えていた。
![(左)熱を電気に変換する熱電変換素子の構造。(右)電気伝導率σとゼーベック係数Sにおけるトレードオフの関係。キャリア濃度を増やしてσを増加させても、Sが減少するため、出力因子に上限が現れる。]()
- 図1.
- (左)熱を電気に変換する熱電変換素子の構造。(右)電気伝導率σとゼーベック係数Sにおけるトレードオフの関係。キャリア濃度を増やしてσを増加させても、Sが減少するため、出力因子に上限が現れる。
片瀬准教授らの研究グループでは、組成がランタン-チタン-酸素の酸化物LaTiO3に対して、「不純物を添加することによって電気特性を変える」という従来の方法ではなく、「人工的に圧力を加えることで電気特性を変える」という新たなアプローチを通して、このトレードオフの相関を破ることを目指した。
研究の手法と成果
「モット絶縁体」の性質を生かした、新たな性能向上アプローチの検討
LaTiO3は、「モット絶縁体」と呼ばれる電気絶縁体であり、電荷の移動を担うキャリアが存在するにも関わらず、電子と電子の電気的な反発力が強いために電子が動けなくなって局在化し、電気を通さない絶縁体となっている。
最近の量子力学に基づく第一原理計算[用語7]によると、このLaTiO3に圧力を加えた場合、電子の局在性が弱まって電子が移動しやすくなり、絶縁体から金属へ変化することが予測されていた。
モット絶縁体には、「電気伝導率:σ」は小さいが「ゼーベック係数:S」は大きいという特徴がある。一方金属は、σは大きいがSは小さいという逆の性質を持っている。そこでLaTiO3に圧力を加え、絶縁体から金属へ変化する境界の状態に置くことができれば、大きなSと高いσを両立させ、高い出力因子を実現できるのではないかと考えた。
薄膜と基板の結合を利用した、LaTiO3への圧力印加
LaTiO3を絶縁体から金属へ変化する状態に保つために、LaTiO3の極薄膜を異なる大きさの格子定数[用語8]を持つ基板上に作製することによって、LaTiO3に人工的な圧力を加え、歪みを制御した。
LaTiO3は図2のようなペロブスカイト型結晶構造を取っている。基板面に対して垂直方向の格子定数をc、面内方向の格子定数をaとすると、歪みがない状態ではcとaの比「c / a比」は1.0である。
ここに歪みを与えるべく、パルスレーザー堆積法[用語9]を用いて、LaTiO3の薄膜を格子定数の異なるペロブスカイト型酸化物基板上にエピタキシャル成長[用語10]させたところ、c / a比を0.992の引張歪みから1.023の圧縮歪みまで制御することができた。さらに、LaTiO3薄膜の厚みを100 nmから4 nmまで極薄化させることによって、最大でc / a = 1.034の大きな圧縮歪みを与えることに成功した。
![薄膜と基板の格子定数の違いを利用し、LaTiO3に格子歪みを加える。格子定数の小さい基板を使うことで、薄膜に対して、面内方向に収縮し、面直方向に伸長する圧縮歪みを加えることができる。]()
- 図2.
- 薄膜と基板の格子定数の違いを利用し、LaTiO3に格子歪みを加える。格子定数の小さい基板を使うことで、薄膜に対して、面内方向に収縮し、面直方向に伸長する圧縮歪みを加えることができる。
さまざまな歪みを加えた、LaTiO3の熱電変換性能
続いて、上記でさまざまな歪みを与えたLaTiO3において、熱電変換材料としての性能の決定要因となる電気伝導率とゼーベック係数の測定を行い、歪みの度合いが出力因子にどのような影響を与えるのかを確認した。
図3aは、室温における電気伝導率とゼーベック係数が、LaTiO3薄膜のc / a比に対してどのように変化するかを示したものである。赤丸の「電気伝導率:σ」に関しては、c / a比の増加に伴って大きく増加し、歪みを与えてないLaTiO3バルク結晶に比べて最大で3桁程度増加することが分かった。ただし、青四角の「ゼーベック係数:S」に関しては、圧縮歪が小さいc / a < 1.028の領域では減少してしまうという、従来のトレードオフの関係に従っていることが明らかになり、図3bに見られるように、出力因子も2.4 μW/mK2を超えなかった。
一方、c / a比が1.028を超える領域では、ゼーベック係数Sが正から負に反転したことから分かるように、電荷の移動を担うキャリアが正孔(p型半導体)から電子(n型金属)に変化した。c / a比が更に増加すると、σとSの両方が同時に大きく増加した。その結果、大きな圧縮歪みを加えたn型LaTiO3では、トレードオフの相関を破ることができ、σとSの両方が増加することで、バルク結晶に比べて出力因子を2桁増加させることができた。
![室温における、LaTiO3薄膜の歪みc / aに対する (a) 電気伝導率σとゼーベック係数S、(b) 熱電出力因子の変化。青色で示す領域はp型伝導、赤色で示す領域はn型伝導を示している。(c) ゼーベック係数Sとキャリア濃度の関係。]()
- 図3.
- 室温における、LaTiO3薄膜の歪みc / aに対する (a) 電気伝導率σとゼーベック係数S、(b) 熱電出力因子の変化。青色で示す領域はp型伝導、赤色で示す領域はn型伝導を示している。(c) ゼーベック係数Sとキャリア濃度の関係。
σとSのトレードオフが破れる起源
図1右で説明した従来の簡単な理論モデルにおいては、「電気伝導率:σ」も「ゼーベック係数:S」もキャリア濃度で決まり、Sの絶対値はキャリア濃度の増大に伴って減少する。
今回の研究で得られた、c / a比の異なる複数のLaTiO3薄膜のゼーベック係数とキャリア濃度の関係を図で示すと図3cのようになり、この関係は従来の簡単な理論モデルで説明できるものであった。
一方、図4で示された電気伝導率とキャリア移動度の変化を見ると、金属化・n型化した領域では、圧縮歪みが大きくなるとキャリア濃度は下がるものの、移動度はそれ以上に2桁も増大することが分かった。
従来の理論モデルでは、「移動度はキャリア濃度に依らず一定である」と考えられていたため、「キャリア濃度が下がるとSは大きくなるものの、σは下がってしまう」というトレードオフの関係は絶対的なものだと捉えられていた。しかし今回の研究により、圧縮歪みを加えたLaTiO3ではキャリア濃度が下がることによってSが大きくなると同時に、キャリア濃度の減少以上に移動度が大きく増大することでσも増大し、トレードオフの関係を破ることが可能なことが明らかになった。
その原因についても、第一原理計算により解明することができた。c / a比の小さい領域では、電気伝導を担うチタン(Ti)の3d軌道が分裂してp型のモット絶縁体になっている(図4左上図)。一方で、c / a比が大きくなる、つまり、圧縮歪が大きくなると、Ti同士の距離が近づき、分裂していたTi 3d軌道が混合することで、電子が動きやすくなり、移動度が大きくなることが分かった。
![LaTiO3薄膜の電気伝導率σとキャリア移動度μの関係。青色で示す領域はp型伝導、赤色で示す領域はn型伝導を示している。上図は、p型LaTiO3とn型LaTiO3の電子構造を比較している。]()
- 図4.
- LaTiO3薄膜の電気伝導率σとキャリア移動度μの関係。青色で示す領域はp型伝導、赤色で示す領域はn型伝導を示している。上図は、p型LaTiO3とn型LaTiO3の電子構造を比較している。
今後の展開
本研究では、人工的な圧力の付加による格子歪みの制御を通して、熱電材料の性能を制限するトレードオフの関係を打ち破り、熱電出力因子を大きく増大させることに成功した。これにより、化学的に安定でありながら、従来は熱電材料としては実用化されていなかった酸化物においても、高性能な熱電材料として利用できる道が見いだせた。
今後は、酸化物の熱電性能をより大きく向上させていくことによって、熱電変換が汎用的なエネルギー源として普及していくことが期待される。
謝辞
この成果は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業 さきがけ「微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の創出」(JPMJPR16R1)により助成されたものである。
用語説明
[用語1]
熱電変換 : 電気を通す金属などの導体や半導体の一部に熱エネルギーを加え、温度差を与えることによって電圧を発生させ、そこから電気エネルギーを取り出す技術。
[用語2]
熱電変換出力因子 : 熱電変換材料の変換効率を計る尺度の一つ。温度差 1℃あたりに発生する熱起電力であるゼーベック係数の 2乗と、電気伝導率の積で表される。
[用語3]
モット絶縁体 : 一般的な絶縁体では、電荷の移動を担うキャリア(電子および正孔)が非常に少ないために電気を通さない。一方、電荷の移動を担えるキャリアが多数存在していても、電子間の電気的な反発力が大きいと、電子がお互いを避けるように局在化し、電気を通さない絶縁体になる。このような絶縁体をモット絶縁体と呼ぶ。
[用語4]
キャリア : 半導体中において電荷を担い、電流を生む粒子。負の電荷を持つ電子と、電子が抜けて正の電荷を持つようになった孔(あな)である正孔がある。
[用語5]
キャリア濃度 : 半導体中において導電性を生じるキャリアである電子、または、正の電荷を持つ正孔の濃度。半導体に添加する不純物の種類によって、電子が伝導するn型と、正孔が伝導するp型のどちらになるかを制御したり、不純物の量によって、電子と正孔のキャリア濃度を変えることができる。
[用語6]
キャリア移動度 : 物質中で電荷の移動を担うキャリアである電子や正孔の動きやすさの指標。単位電圧あたりのキャリアの速度で定義され、移動度が大きいほど電気伝導率が上がる。
[用語7]
第一原理計算 : 量子力学の基本原理に基づいた計算。この手法を用いると、物質の性質を支配する電子の状態だけでなく、構造の全エネルギーを計算でき、結晶や分子の構造や安定性なども予測可能になる。
[用語8]
格子定数 : 結晶を構成する最小のユニット(単位格子)の大きさ。
[用語9]
パルスレーザー堆積法 : 原料物質に対して紫外パルスレーザーを照射し、蒸発気化させながら基板上に堆積させることによって、原料物質の薄膜を成長させる合成法。
[用語10]
エピタキシャル成長 : 単結晶基板結晶の上に、結晶方位を合わせて薄膜結晶を成長させる技術。格子定数がわずかに異なる基板上に高品質な結晶を成長させることで、薄膜面の内部の方向に数万気圧に相当する圧力を加えることができる。
論文情報
掲載誌 : |
Advanced Science(アドバンスド サイエンス) |
論文タイトル : |
Breaking of thermopower–conductivity trade-off in LaTiO3 film around Mott insulator to metal transition
(和訳:LaTiO3薄膜のモット絶縁体-金属転移近傍における、ゼーベック係数と電気伝導度のトレードオフの破れ) |
著者 : |
Takayoshi Katase1,2,*, Xinyi He1, Terumasa Tadano3, Jan M. Tomczak4, Takaki Onozato5, Keisuke Ide1, Bin Feng6, Tetsuya Tohei7, Hidenori Hiramatsu1,8, Hiromichi Ohta5, Yuichi Ikuhara6, Hideo Hosono8, and Toshio Kamiya1,8,*
(片瀬貴義1,2,*、ホー シンイ1、只野央将3、トムザック ジャン4、小野里尚記5、井手啓介1、フェン ビン6、藤平哲也7、平松秀典1,8、太田裕道5、幾原雄一6、細野秀雄8、神谷利夫1,8,*) |
所属 : |
1. 東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所
2. 科学技術振興機構 さきがけ
3. 物質・材料研究機構
4. ウィーン工科大学 物性研究所
5. 北海道大学 電子科学研究所
6. 東京大学 工学系研究科 総合研究機構
7. 大阪大学 基礎工学研究科
8. 東京工業大学 元素戦略研究センター
|
DOI : |
|











![図2 MetaPlatanusでのみ全長近くのゲノム配列が決定できた例 ヒトの口腔内サンプルに対する結果。対応する生物種はレンサ球菌であるStreptococcus salivarius[用語11]で、今回のサンプル内で多量に存在していると推定される。配列決定の結果が分断されている場合、対応する図中の線も途切れる。近縁株の参照配列は、大まかな配列の正確性を見積もるために表示。](http://www.titech.ac.jp//news/img/news-28585-b.png)