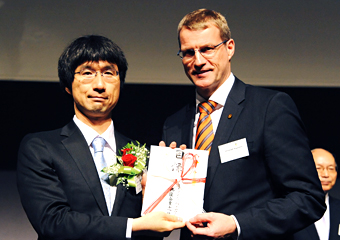今年で3回目を迎えるホームカミングデイも、卒業生同士・卒業生と大学・卒業生と現役学生の交流を促す年間行事として定着しつつあります。今回は地域や一般の方にもご参加いただける企画を設けたことで、交流の場として、さらに充実したものとなりました。

すずかけ台キャンパス
すずかけ祭との同時開催
5月17日(土)には、すずかけ祭との同時開催で「ホームカミングデイ2014すずかけ台」として特別講演会(日刊工業新聞社論説委員兼科学技術部編集委員 山本佳世子氏、東工大理工学研究科小長井誠教授)と全体交流会(大学会館3階ラウンジ)が開催され、多くの卒業生、現役教職員、現役学生が集まり盛況でした。
5月25日(日)には、「ホームカミングデイ2014大岡山」が開催され、数日前の降雨で心配された天気にも恵まれ、多くの卒業生、現役教職員、現役学生が集まりました。今回から東急線大岡山駅構内、すずかけ台駅構内の横断幕・ポスターや、大岡山北口商店街振興組合のご協力を得て商店街内にもポスターを掲示していただき、50名以上の一般参加者にも参加いただきました。

大岡山キャンパスでのホームカミングデイ
午前中から、徒歩で「ものつくりセンター」やスーパーコンピューター「TSUBAME」を見学するキャンパスツアー、バスで大岡山地区、緑ヶ丘地区を周遊するバスツアー、図書館内の見学ツアーが実施され、懐かしいキャンパスの「今」を御覧いただきました。
正午からは学生による演奏会が70周年記念講堂で行われ、前半はラテンジャズビッグバンド「ロス・ガラチェロス」による思わず踊りだしたくなるような演奏、後半は混声合唱団「コール・クライネス」の何度も全国優勝をしているハーモニーでオーディエンスを魅了しました。

キャンパスツアー
(スーパーコンピュータTSUBAMEにて)
演奏会に続いて特別講演会が開かれ、前半はNTT東日本代表取締役社長 山村雅之氏による講演「お客様をつなぎ続けるために~東日本大震災を経験して~」で、いかなる時も「つなぎ続ける」使命を果たすため、同社が一丸となって復旧に取り組んだお話と動画が会場の感動を呼び、質疑応答も活気あるものとなりました。後半は2012年に設立された「地球生命研究所」所長・廣瀬敬教授による「地球の起源と生命の起源」。「地球外生命体は存在するか?」というSFチックなお話もアカデミックかつ夢をもって語られ、知的好奇心をそそる講演に会場の質問も後を絶ちませんでした。

混声合唱団コール・クライネス
ホームカミングデイ当日は学生サークルによる企画も盛りだくさんで、じゃぐテックによるジャグリングの披露、東工大ボランティアグループによる震災対応アプリの展示、茶道部による呈茶、自動車部による懐かしの名車の展示、東工大マイスターによる電気自動車「エコノムーブ」のデモ走行、西9号館では「ものつくりサークル大集合」企画が実施され、そしてグラウンドではサッカー部による公式戦も開催され大学イベントをさらに盛り上げてくれました。

ものつくりサークル大集合(西9号館)
16:30からは東工大蔵前会館(TTF)1階全フロア貸切で全体交流会が開かれ、会場には学科・分野別のテーブルが用意され、懐かしい顔ぶれによる旧交を温める場面に加え、現役学生とOBによる世代を超えた交流も会場の至るところで見られました。今年から学科・分野別テーブルに加え、サークルや学生交流プログラムOBのテーブルも用意され、陸上部、燕弓会、JAYSESのテーブルも設置され、若いOBや現役学生の交流が見られました。交流会冒頭、三島良直学長、庄山悦彦蔵前工業会理事長、小野功副学長の挨拶に続き、石田義雄蔵前工業会理事・東京支部長による乾杯の御発声、続いて男声合唱団シュヴァルベンコールOBによる合唱が交流会に華を添えました。
東工大と蔵前工業会共催によるホームカミングデイ2014は18:00に全体交流会の閉会とともに締めくくられ、卒業生と大学の絆を強める象徴的なイベントとして参加者の心に刻まれたことでしょう。

全体交流会会場(くらまえホール)
お問い合わせ先
東工大ホームカミングデイ事務局
Tel: 03-5734-2414
Email: hcd.ooka@jim.titech.ac.jp