9月3日に日本テレビ系列で放送された「鳥人間コンテスト2014」。
人力プロペラ機ディスタンス部門に東工大マイスターが連覇をかけて出場しました。当日、まさかの天候不順により多くのチームが飛行できず、大会は不成立となりました。
マイスターの活動は鳥人間コンテストを境に新旧メンバーが入れ替わります。今夏で活動を終えた3年生に集まってもらい、今年の機体について、コンテストを終えた感想について話を聞きました。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
主将(代表) 杉本大河さん(機械科学科3年生)
全体設計 岡部紘介さん(機械宇宙学科3年生)
パイロット 大槻恒太さん(高分子工学科3年生)
翼班 石原和輝さん(国際開発工学科3年生)
駆動班 秦悠人さん(機械宇宙学科3年生)
FRP(翼の骨組)班 京田浩平さん(有機材料工学科3年生)
- 鳥人間コンテスト、おつかれさまでした。天候不順という難敵が現れ、大変残念な結果となりました。まずは、大会の様子を教えてください。
琵琶湖には前日に到着し、機体を組み立て、機体審査を受けました。審査をパスし、一度機体を解体した後、睡眠をとりにホテルに戻りました。空はすでに荒れていて、翌日の天気予報はギリギリ飛べるかどうか。予報が良い方向に傾けば飛べるかな、と思っていました。この段階では飛べないとは思っていませんでした。
人力プロペラ機ディスタンス部門は朝6時から始まります。われわれのフライトは11時〜12時ぐらいの予定でしたので、機体を組み立て、待機しました。6時の段階で、ちょっと厳しいかな、という天候でした。まずは3チームが飛びましたが、どのチームも苦戦していました。飛んだチームのパイロットに聞くと、かなり風にあおられ、浮いているのがやっとだったそうです。その後、風が強くなり、一時競技を止め、待機していると、そのうちに雨まで降ってきました。雷の予報が出たので、避難するよう本部から指示があり、バスに避難しました。やがて雷が鳴り始め、激しい雨が降り続きました。
雷雨は1時間ほどで止みましたが、本部に呼ばれ、「これから天気が悪化する予報なので、機体を組み上げた順に飛ばすことにする」と言われました。この時点で、あまりの風の強さにパイロットの安全のため棄権するチームや、待機中に機体が壊れたチームも出ていました。東工大チームは雨を避けるため一度解体していた機体を再度組み上げ、待機していましたが、遂に本部から競技中止が発表されました。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
大会当日の様子
- “中止”と発表されたときの気持ちは?
Clik here to view.
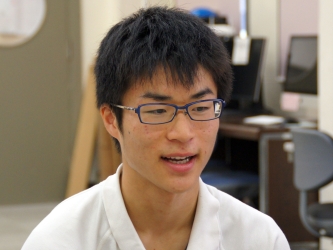
大槻さん
杉本さん(代表・フレーム班): 仕方がないかな、と思いました。
大槻さん(パイロット): 今年の機体は性能が良かったので、無理に飛ばして、壊してしまうよりは、完璧な状態で持って帰って他で飛ばしたいと思っていました。風がよければ長距離フライトができると思っていたので、中止はかえってラッキーだと思いました。
- 今年の機体の特長を教えてください。
Clik here to view.

岡部さん(左)、杉本さん(右)
岡部さん(全体設計): 一言でいうと、“高性能”。翼の設計の仕方を大幅に変えて、翼の抵抗を一気に減らしました。
杉本さん(代表・フレーム班): マイスター史上最高の機体を目指しました。
大槻さん(パイロット): テストフライトでの感触がとにかく良かったです。滑空比が良すぎて、漕ぐのをやめても機体が落ちてこない。慣性でプロペラが回っているので、ペダルに足が付いていっているだけでしたが、機体を支える人を配置している最後のラインまで機体が到達してしまったほどでした。
- 2年半のマイスターでの活動を振り返って、いかがですか?
Clik here to view.

今年の機体「宙(ソラ)」、コックピット部分
杉本さん(代表・フレーム班): マイスターの活動は、企業からの援助、先生方からの指導、学長や蔵前工業会からの激励など、多くの方々に支えられています。その分プレッシャーも大きいです。代表として1年過ごすと本当に疲れます。途中から早く終わらないかなという気持ちになりますが、そこを踏ん張れば、何か素晴らしい景色が見られるはず、だったのですが。この一か月ずっと消化不良です。何とか消化できる終わり方にしたいと思っています。現在、私たちの機体を飛ばすために模索中です。
岡部さん(全体設計): ここまで色々あったな、と。そして、せっかく作った機体が長距離飛んだところを見てみたいと思ったりしています。一方で、設計とか機体制作の統括はもうやらなくてもいいかな、と思います。それくらい色々ありました。
大槻さん(パイロット): 以前は制作をやっていましたが、制作から離れて1年間トレーニングしてきました。トレーニング中には、他のメンバーが優しく励ましてくれました。大会後は、体力維持を兼ねてトライアスロン部に入りました。まだ機体が残っていますし、テストフライトがすごく良かったので、飛べる機会があれば、絶対、長距離飛んでみせます。
石原さん(翼班): 昨年、代替わりしてから、みんなで良い機体を作ろうとがんばってきました。鳥人間コンテストを楽しみにしていたので残念ですが、やることはやったので後悔はないです。
秦さん(駆動班): 駆動班はそんなにハードではないので、基本的に楽しく活動してきました。大変そうにしているメンバーの話を聞いたりして、チームとしての一体感が出ていたと思います。
京田さん(FRP班): FRP班は週一で徹夜作業でしたが、楽しく活動しました。2年半、マイスターにいただけでも東工大に来て良かったと思っています。
Clik here to view.

京田さん(左)、秦さん(右)
Clik here to view.

石原さん
東工大マイスター 2014年5月3日 第3回テストフライト
(動画が正しく表示されない場合は最新版のブラウザでご覧ください。)
Image may be NSFW.
Clik here to view.
杉本さん
代表から新代表へのエール
代表に就任したら、即、代表になれるのでなく、だんだん代表になっていくもの。これから1年は心労がたまる一方で、2月~3月がピークです。僕たちは、後輩に大会3連覇の挑戦権を与えるつもりでやってきました。今年は競技不成立で優勝なしだったので、マイスターは来年もディフェンディング・チャンピオンです。連覇目指してがんばって!
Image may be NSFW.
Clik here to view.
田中さん
新代表より
田中翔汰さん(機械宇宙学科2年)
来年は優勝を目指します。新パイロットも優勝してみんなで喜びたいと言っています。みんなで協力して1年やっていきます。
先輩から後輩へ、マイスターの魂は引き継がれていきます。
Image may be NSFW.
Clik here to view.


























































