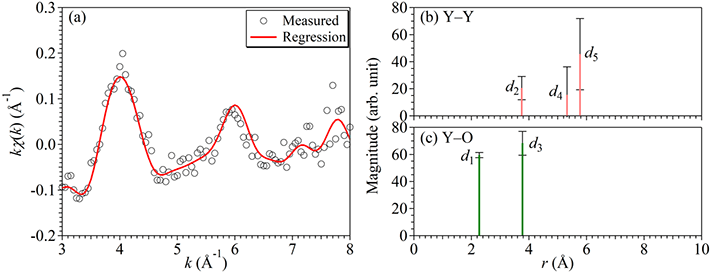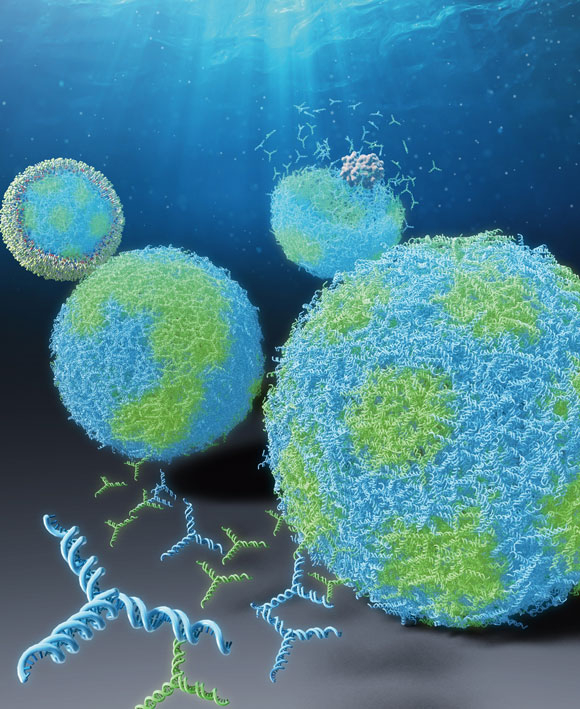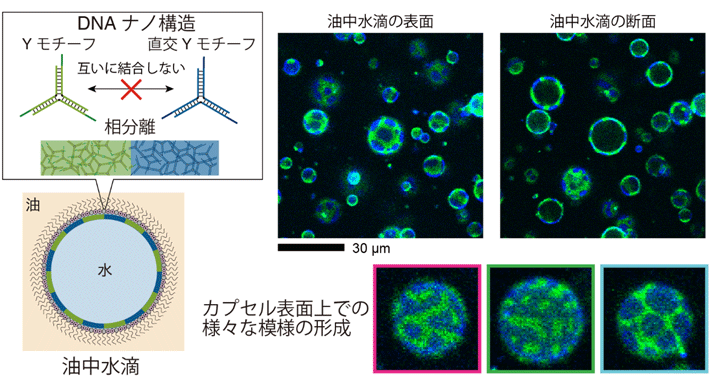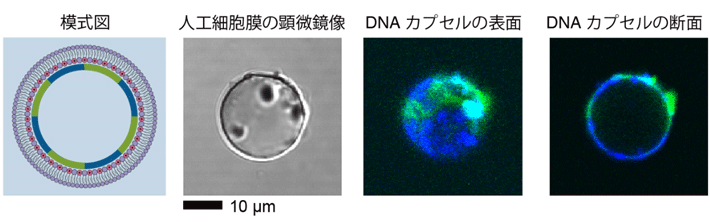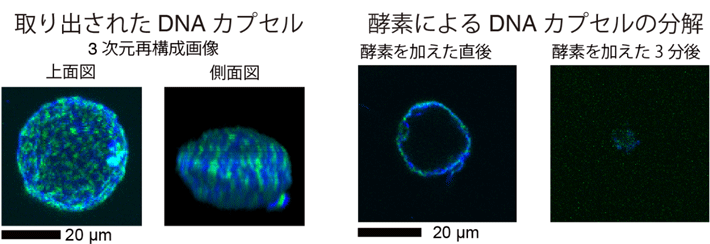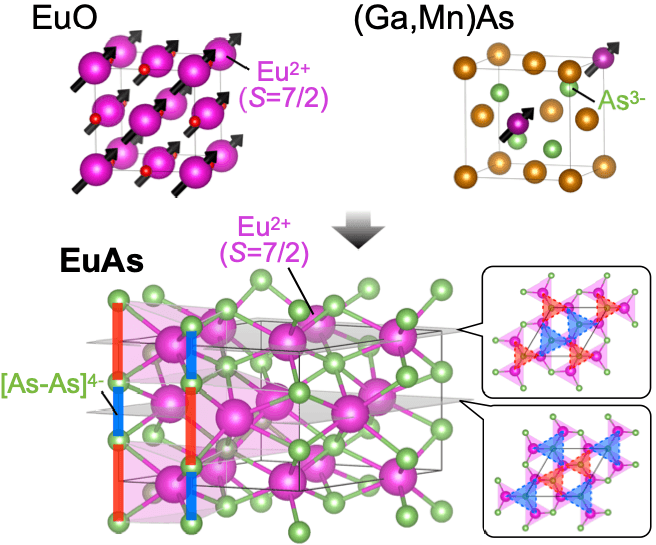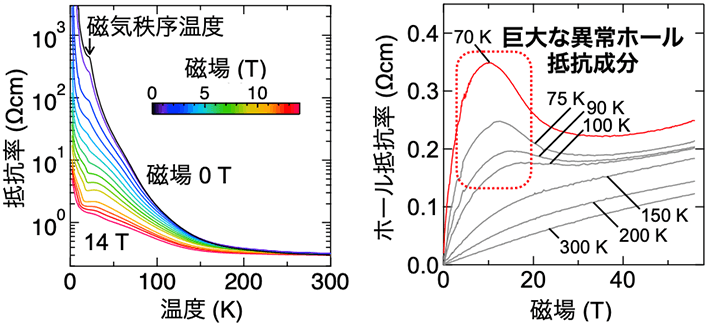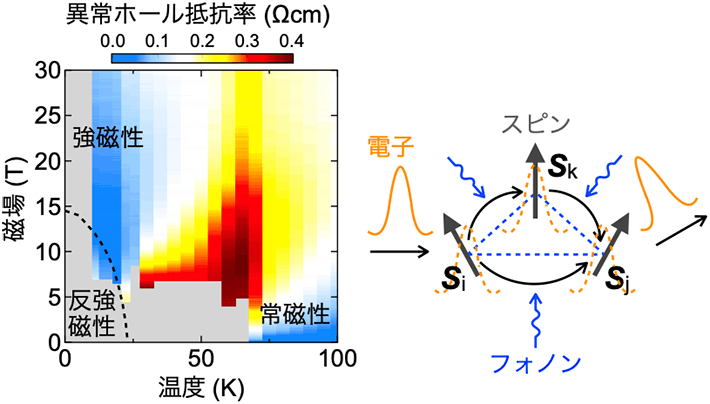東京工業大学は、11月17日、2021年度永年勤続者表彰式を行いました。この表彰は、永年、職務に精励した職員を対象とするものです。永年勤続とは、他の国立大学等を含む勤続20年、うち本学勤務が10年以上を指します。今回表彰された方は常勤職員9名、無期雇用職員3名の計12名でした。なお、本年度より大学教員は表彰の対象外となりました。
表彰式では、益一哉学長から一人ひとりに表彰状の授与が行われ、永年の功労に対して祝辞が贈られました。表彰式は新型コロナウイルス感染症対策のため、常勤職員、無期雇用職員に分かれて行いました。

常勤職員の表彰式

益学長から表彰される永年勤続の職員
今回表彰された方々は次のとおりです。
|
所属 |
職名 |
氏名 |
|---|---|---|
|
広報課広報推進グループ |
グループ長 |
池谷大輔 |
|
広報課広報推進グループ |
主任 |
三瓶由紀子 |
|
契約課大岡山第1契約グループ |
グループ長 |
小倉弘樹 |
|
国際連携課企画・調整グループ |
グループ長 |
鶴島裕子 |
|
研究推進部研究資金支援課 |
課長 |
植松明彦 |
|
研究推進部産学連携課 |
専門職 |
楠瀬悟之 |
|
情報基盤課情報セキュリティ対策グループ |
主任 |
森谷寛 |
|
リベラルアーツ研究教育院業務推進課リベラルアーツ研究教育院事務グループ |
主査 |
高田友秀 |
|
オープンファシリティセンター |
技術専門員 |
庄司大 |
|
科学技術創成研究院 |
事務限定職員 |
三村育久代 |
|
主計課総務・監査グループ |
事務限定職員 |
中村惠理子 |
|
ものつくり教育研究支援センター |
事務限定職員 |
横小路京子 |
(所属順・敬称略)

常勤職員の記念撮影

無期雇用職員の記念撮影
- 2020年度永年勤続者表彰式 職員59名を表彰|東工大ニュース
- 2019年度永年勤続者表彰式にて職員46名を表彰|東工大ニュース
- 令和元年度 大学の業務運営に貢献した職員25名を表彰|東工大ニュース
- 平成30年度 大学の業務運営に貢献した職員を表彰|東工大ニュース