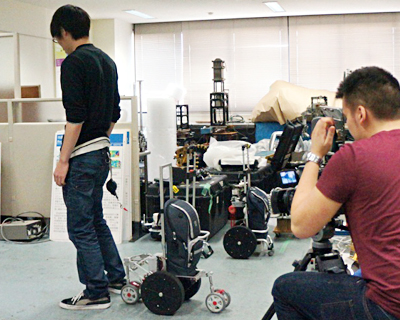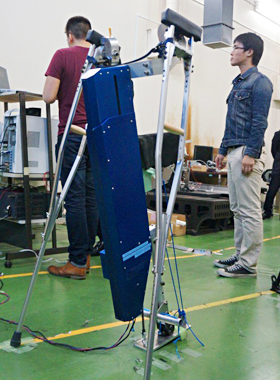「38年前の今日は何が起こった日か分かりますか?」というフリーアナウンサーの吉田填一郎さんの問いかけからこのスポーツ講座は始まりました。すこしだけ間があった後、山本浩二さんが「そうだ今日は10月15日、カープが初優勝した日ですね」と答えた。このあと吉田さんの問いかけに答えるかたちで進んでいきました。
山本浩二さん広島カープ入団の頃の話
![]()
「当時はお立ち台はなく、また、グランドに観衆が入ってきて胴上げはできなかったですね。優勝する前は、大洋(今の横浜)、ヤクルト、広島でいつも最下位争いをしていました。カープに入ったころはプロ野球の選手になったから練習や試合のないときは豪勢に遊べると思っていたら、とんでもない話でした。当時の根本監督は何年か後の優勝を狙っていて、徹底的に練習をさせられ、休めるのは正月3が日だけでした。でもあとから思えばこれはよかったと思います。たとえば衣笠のようなライバルがいました。そのころは自分さえよければ年俸もあがるし、ライバルの成績が上がることは望んでいませんでした。そのころのカープはその名にちなんで「鯉のぼりまで」とよく言われていました。五月の連休が終わるころにはペナントレースの下位グループの常連だったからです。でも優勝した1975年は違いました。6月7月8月になっても優勝争い。前の年だったら衣笠に「打つなよー」と思ったかもしれないがその年はチームが一つになっていたので「打ってくれよー」に変わりました。その優勝を境にライバルたちと腹を割ってはなせる、技術について話し合える、練習を遅くまで競い合うといういい関係になりました。後輩たちもそれを見て熱心に練習していたと思います。」
最近のカープの話
「カープ強いですよ。軸がしっかりしている、「キクチ」覚えておいてください。身体能力がすごい。なんでも食らいついていく。頭を使えばもっとすごい。カープ、クライマックスシリーズミスなしです。走塁もいい。自信を持っています。下剋上(ペナントレースで下位がクライマックスシリーズで勝つこと)ありますよ。カープの野村監督は前半、たたかれました。ツイッターなんか好き勝手なことを書きますからね。野村監督は失敗しても若い人を使った。その積み重ねで今の強いチームになった。マスコミなんか書きたい放題なので現場はいい加減にしてくれと思ってますよ。ある記者はカープの前半ぼろくそに書いておいてAクラスに入ると手のひら返しですよ。」
WBCのこと
![]()
「昨年の10月10日に監督に決まったのですが、それまでは記者がうちの周りに集まって大変でした。それで決まったら記者が来なくなり、静かになりました。コーチの人選ですが、まず最初にウマの合う東尾をコーチにしました。それから選手の人選。選手は「山本浩二」の名前は知っていても性格は知りません。それで12球団のキャンプをすべて回りました。練習を始めても最初の数日は選手も遠慮がありました。食事を一緒にしてうちとけるようになりました。大変だったのは33人から28人に減らすとき。減らした日に決起集会を開きました。そのとき、減らされた5人も参加してくれて、特に「村田」が勇気づけてくれました。それから侍ジャパンは33人という意識で、チームが結束しました。
第1戦はブラジルでした。負ける相手ではないのですが、相手ピッチャーがよかった。ようやく8回に逆転して勝てました。短期決戦の難しさを感じました。
台湾戦では9回の2アウト、鳥谷に盗塁のサインを出していました。いつでも走っていいというのをグリーンライトというのです。これでした。そのあと井端。ショートの後ろが空いていると思ったらそこに打った。半分は負けコメントを考えていましたよ。そして10回。中田のホームラン。これでいけると思いました。
![]()
ところで、アメリカのバッシングはひどかったですね。最初は35度もあるフェニックスで2試合、そのあとサンフランシスコでナイター、このときは10度ないくらいです。アメリカの策略じゃないでしょうかね。
準決勝は3:1で負けました。内川が盗塁失敗しましたが、これは予め打ち合わせていた通りに走っただけです。盗塁できるかどうかはピッチャーのモーションからキャッチャーにボールが届くのに1.4秒以内かどうかなんです。ところが、この時にピッチャーは1.8秒くらい。そこでこのピッチャーが出てきたらグリーンライトなのです。でも2塁の井端が一瞬躊躇した。内川は自分がアウトにならないように懸命に走っていただけなんです。
試合で負けた後の新聞記者の手のひら返しはまいりました。でも広島に帰ると皆さんが握手してくれました。本当にこの年になってユニホームを着て燃えることができてよかったと思います。」
このあと、吉田アナウンサーの問いかけや学生の質問に答えて選手、監督、中継のアナウンサーのさまざまな個性について話していただき、スポーツ講座が終了しました。お二人の軽妙な語りで楽しく、興味深い時間を過ごすことができました。
![]()