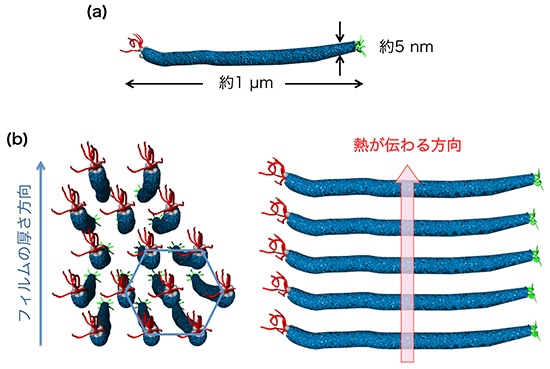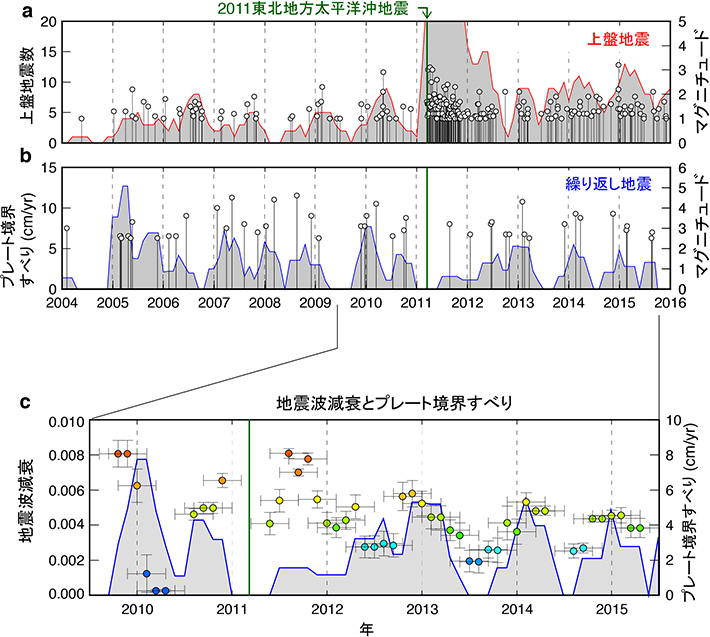発表のポイント
- 日本の南鳥島周辺の排他的経済水域(EEZ)内に存在するレアアース泥の資源分布を可視化して資源量を把握し、世界需要の数百年分に相当する莫大なレアアース資源が存在することを明らかにしました。
- 粒径分離によってレアアース濃集鉱物を選択的に回収する技術の確立に成功しました。この技術により、中国陸上レアアース鉱床の20倍程度まで品位を向上させることが可能となりました。将来的には、濃集鉱物のみを回収することで50倍以上の品位にすることを目指します。
- 本研究の成果により、再生可能エネルギー技術やエレクトロニクス、医療技術分野など最先端産業に必須となるレアアース資源開発の経済性が大幅に向上することが期待されます。
早稲田大学 理工学術院 髙谷雄太郎講師、東京大学工学系研究科 加藤泰浩教授らの研究チームは、千葉工業大学、国立研究開発法人海洋研究開発機構、東亜建設工業株式会社、太平洋セメント株式会社、東京工業大学、神戸大学と共同で、南鳥島周辺海域レアアース泥の資源分布の可視化とそれに基づく資源量の把握を行い、世界需要の数百年分に相当する莫大なレアアース資源が存在することを明らかにしました。さらに、レアアース濃集鉱物を選択的に回収する技術の確立に成功しました。
レアアース元素[用語1]は「産業のビタミン」とも呼ばれ、再生可能エネルギー技術やエレクトロニクス、医療技術分野など、日本が技術的優位性を有する最先端産業に必須の金属材料です。一方、レアアースの世界生産は依然として中国の寡占状態にあり、その供給構造の脆弱性が問題となっています。新興国を中心に今後もレアアースの需要が伸び続けることが予測される中、レアアース資源の安定的な確保は不可欠で、日本の排他的経済水域内(EEZ)におけるレアアース泥[用語2]の分布およびレアアース資源量の正確な把握が望まれていました。
本研究チームは、南鳥島EEZ南部海域に存在する有望エリアのレアアース資源分布を初めて可視化することに成功しました。特に、北西に位置する一角に極めてレアアース濃度の高い海域が存在することを確認し、このエリア(約105 km2)だけでも、レアアース資源量は約120万トン(酸化物換算)に達し、最先端産業の中で特に重要なジスプロシウム、テルビウム、ユウロピウム、イットリウムは現在の世界消費の57年分、32年分、47年分、62年分に相当することが分かりました。また、有望エリアの全海域(約2,500 km2)を合算すると、その資源量は1,600万トンを超え、当該エリアが莫大なレアアース資源ポテンシャルを持つことが明らかになりました。さらに、本研究チームは、レアアースの大半が含まれる生物源のリン酸カルシウム[用語3]が、レアアース泥中の他の構成鉱物に対して大きな粒径を持つことに着目し、粒径分離によってレアアース泥中の総レアアース濃度を最大で2.6倍にまで高めることに成功しました。粒径分離によって泥の重量が大幅に減少するため、海上への揚泥や製錬のコストの削減も期待されます。
本研究で提示したように、レアアース泥の粒径選鉱を行うことによってレアアース泥開発の経済性を大幅に向上させることが可能になります。さらに、日本のEEZに莫大なレアアース泥が確認されたことは、我が国の資源戦略に対しても極めて大きなインパクトを与えます。本研究成果をもとに将来的に南鳥島レアアース泥の開発が実現すれば、日本のみならず世界においても海底鉱物資源の開発が進展するとともに、レアアースを活用した多様な最先端産業の発展・創出といった波及効果が期待されます。
本研究成果は英国Nature Publish Groupのオンライン科学誌『Scientific Reports』に4月10日10時(現地時間)に掲載されました。
これまでの研究で分かっていたこと(科学史的・歴史的な背景など)
レアアース(希土類)元素は、原子番号57番~71番までのランタノイド15元素に、原子番号21番のSc(スカンジウム)、39番Y(イットリウム)を加えた全17元素の総称です。本論文ではScおよび天然にほとんど存在しないPm(プロメチウム)を除く15元素をREY(Rare-Earth elements and Yttrium)と表記しています。レアアース元素は「産業のビタミン」とも呼ばれ、再生可能エネルギー技術やエレクトロニクス、医療技術分野など、我が国が技術的優位性を有する最先端産業に必須の金属材料です。一方、レアアースの世界生産は依然として中国の寡占状態にあり、その供給構造の脆弱性が問題となっています。新興国を中心に今後もレアアースの需要が伸び続けることが予測される中、レアアースの新規供給先の確保は我が国にとって国家的な命題になっています。このような中、2011年にKato et al.(2011)によって、レアアースを高濃度で含有する海底堆積物(レアアース泥)が太平洋の広域に分布することが『Nature Geoscience』で報告されました。さらに2013年には、南鳥島周辺の日本の排他的経済水域内(Exclusive Economic Zone, EEZ)で、総レアアース濃度(ΣREY)が7,000 ppmに達する超高濃度レアアース泥の存在が確認され、新規レアアース資源として大きな注目を集めています。超高濃度レアアース泥はレアアースを高濃度で含有する生物源のリン酸カルシウム(Biogenic Calcium Phosphate, BCP)を多く含み、これがレアアース濃集の鍵であることが明らかにされていました。これらの発見を踏まえ、将来の開発実現に向けて、我が国EEZ内におけるレアアース泥の分布およびレアアース資源量の正確な把握が望まれていました。
今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと
超高濃度レアアース泥の発見を受け、2013~2015年にかけて国立研究開発法人海洋研究開発機構の研究船(みらい、かいれい)により、南鳥島EEZ内の詳細な調査が実施されました(図1)。本研究では、2014~2015年までに実施された計3航海(MR14-E02、MR15-E01、MR15-02)で採取された23本の堆積物コアから、新規に573試料の化学分析を行いました。さらに、すでに公表されていた104試料(KR13-02航海で採取された2本の堆積物コア試料)のデータを加え、陸上の鉱床評価にも用いられているGISソフトウェア(Geographic Information System Software)である「ArcGIS」により、南鳥島の南方沖約250 kmの超高濃度レアアース泥分布域における深海堆積物中のレアアース濃度分布を可視化するとともに、資源量の把握を行いました。
![本研究で用いたコア試料の採取地点]()
図1. 本研究で用いたコア試料の採取地点
左図点線は日本の排他的経済水域を示す。また、右図の白枠で囲まれた地域を有望海域として設定したエリア(アルファベットと数字の組合せにより、A1-D6に区分した)。
また、本研究ではレアアース泥の経済的価値の向上を目的とした選鉱手法についても検討しました。レアアースがどの鉱物に含まれているかを把握するため、超高濃度レアアース泥に特徴的に含まれるBCPおよび十字沸石(沸石鉱物の一種)の化学組成をレーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量分析法(LA-ICP-MS)および電子線マイクロアナライザ(EPMA)によって分析しました。この結果、レアアース泥中におけるレアアースの大半がBCPに含まれていることが明らかになりました。BCPはレアアース泥中の他の構成鉱物に対して有意に大きな粒径を持つことが先行研究によって確認されています。そこで、粒径分離によってBCPを選択的に回収し、レアアースの濃縮(選鉱)を行うことが可能かを確認するとともに、実開発を見越して既に工業的に用いられているハイドロサイクロン[用語4]と呼ばれる分級装置を用いてレアアース泥の選鉱実験を行いました。
今回の研究で得られた結果及び知見
本研究によって、南鳥島EEZ南部海域に存在する有望エリア(北緯21°48'-22°15'、東経153°30'-154°07'の約2,500 km2の海域)のレアアース資源分布が初めて可視化されました(図2)。この結果、有望エリア内でも特に、北西に位置する一角(図2のB1エリア、約105 km2)に極めてレアアース濃度の高い海域が存在することが確認されました。B1エリアにおけるΣREYは、海底面下5〜6 mでは平均で5,600 ppmに達し、海底面から深度10 mまでの平均でも1,700 ppmを超える値を示しました。このエリアだけでも、レアアース資源量は約120万トン(酸化物換算)に達し、最先端産業の中で特に重要なジスプロシウム、テルビウム、ユウロピウム、イットリウムは現在の世界消費の57年分、32年分、47年分、62年分に相当することが明らかになりました。また、有望エリアの全海域を合算すると、その資源量は1,600万トンを超え、当該エリアが莫大なレアアース資源ポテンシャルを持つことが明らかになりました。
本研究ではさらに、レアアース泥の選鉱による経済性向上の可能性を検討しました。上述の通り、LA-ICP-MSおよびEPMAによる分析の結果、BCPが南鳥島EEZ内のレアアース泥中においてレアアース元素の大部分を保持していることが明らかになりました。BCP中のΣREYは最大で22,000 ppmを超え、平均でも15,000 ppmを超える高い値を示すことから、BCPを選択的に回収することでレアアース泥の品位を大幅に向上させることが可能であると考えられます。レアアース泥中において、BCPは他の構成鉱物に比較して有意に大きな粒径を示します。そこで本研究では、まず単純な篩分けによるレアアース泥の粒径分離実験を行いました。その結果、泥から20 µm以上の大きさの粒子を分離することで、BCPを効率的に回収できることが明らかになりました(図3)。この結果を受け、粒径分離によるBCPの選択的回収を実開発スケールに拡張するため、工業的に広く利用されているハイドロサイクロンを用いた粒径選別試験を実施しました(図4〜5)。ハイドロサイクロンによる選鉱試験の結果は、篩分けによる粒径分離試験の結果と調和的であり、レアアース泥のΣREYを最大で2.6倍(2,315 ppm → 6,030 ppm)にまで高められることが確認されました(図5)。これは、中国の陸上鉱床で開発されているレアアース鉱石(300 ppm以上)の20倍に達する値です。さらに今後、BCPのみを完全に分離する技術が確立されれば、その品位は中国鉱床の約50倍にまで高められる可能性があります。また、粒径分離によって泥の重量が大幅に減少するため、海上への揚泥や製錬のコストの削減も期待されます。一連の実験は、本研究で提示したレアアース泥の粒径選鉱によってレアアース泥開発の経済性を大幅に向上させるとともに、当該選鉱手法を実開発スケールに拡張可能なことを示しました。
![有望エリアにおける海底面からの深度別レアアース濃度分布図]()
図2. 有望エリアにおける海底面からの深度別レアアース濃度分布図
B1エリア(赤枠で表示、約105 km2)が最も高い総レアアース濃度を示す。
![篩(ふるい)を用いた粒径分離実験結果]()
図3. 篩(ふるい)を用いた粒径分離実験結果
結果は、レアアース泥(ΣREY: 400〜2,000 ppm)、高濃度レアアース泥(ΣREY: 2,000〜5,000 ppm)、超高濃度レアアース泥(ΣREY: 5,000 ppm 以上)に分けて表示。いずれの試料でも、20 µm以下の粒径は総レアアース濃度が最も低く重量比も大きいことから、20 µmを基準として分級することでレアアース泥の品位を向上できることが分かる。
![ハイドロサイクロンを用いた分級試験の様子]()
図4. ハイドロサイクロンを用いた分級試験の様子
写真奥にある大きな容器内にレアアース泥を海水中で解泥したスラリーが入っている。写真中央に写るハイドロサイクロンにスラリーを送り込み分級を行う。ハイドロサイクロン下部にアンダーフロー(20 µm以上の粒子)、左の容器にオーバーフロー(20 µm以下の粒子)が排出される。
![ハイドロサイクロンを用いた分級試験結果]()
図5. ハイドロサイクロンを用いた分級試験結果
分級による品位向上率は最大で2.6倍に達し、レアアース泥の経済的価値を大きく向上させられることが確かめられた。
研究の波及効果や社会的影響
本研究は、量(資源量)と質(鉱物学的な特長を生かした選鉱が可能)の両面からレアアース泥の莫大な資源ポテンシャルを明らかにしました。この成果により、従来は基礎研究の範疇に留まっていた海底鉱物資源を、現実的に開発可能な資源として初めて議論の俎上に載せることに成功したと考えています。持続可能な社会の発展に向けては、レアアース資源の安定的な確保が不可欠です。レアアース泥は我が国のEEZ内に存在することから、我が国の資源戦略に対しても極めて大きなインパクトを与えます。本研究成果をもとに将来的に南鳥島レアアース泥の開発が実現すれば、日本のみならず世界においても海底鉱物資源の開発が進展するとともに、レアアースを活用した多様な最先端産業の発展・創出といった波及効果が期待されます。
今後の課題
本研究によって、レアアース泥が実開発の対象として十分な資源量を有し、さらに粒径選鉱によって大幅にその経済性を向上させられることが明らかとなりました。レアアース泥の開発に向けた次のステップは、深海底に存在するレアアース泥を採掘し海上に運んでくるための採泥・揚泥技術の開発になります。採泥・揚泥技術の検討は、すでに産官学の協力のもと進められており、効率的・経済的な手法が精力的に検討されています。また、採泥・揚泥技術と並行して、本研究成果を踏まえた資源開発プロジェクトの詳細な経済性評価も重要な課題となります。
用語説明
[用語1] レアアース : レアアース(希土類)元素は、原子番号57番~71番までのランタノイド15元素に、原子番号21番のSc(スカンジウム)、39番Y(イットリウム)を加えた全17元素の総称です(ただし、原子番号61番のPm(プロメチウム)は自然界にはほとんど存在しません)。本論文ではScとPmを除く15元素をREY(Rare-Earth elements and Yttrium)と表記しました。レアアースは独特な光学的特性や磁気的特性を持つことから、ハイブリッドカーのモーターに使われるNd-Fe-B磁石やLEDの蛍光体などの最先端グリーン・テクノロジー(省エネ・エコ技術)に不可欠な元素であり、これらの最先端技術を基幹産業とする我が国にとっては極めて重要な金属資源です。
[用語2] レアアース泥 : 2011年に東京大学の加藤泰浩教授らにより発見された、新しいタイプの海底鉱物資源。レアアースを高濃度(総レアアース濃度400 ppm以上)で含む深海堆積物の総称であり、総レアアース濃度が2,000 ppmを超えるものは高濃度レアアース泥、5,000 ppmを超えるものは超高濃度レアアース泥と定義されています。レアアース泥は、資源として以下のような特長を有します。
- 1.
- 高い総レアアース濃度を示し、特に産業上重要な重レアアースに富むこと
- 2.
- 太平洋の広範囲に分布するため膨大な資源量が見込まれること
- 3.
- 遠洋性の深海堆積物として層状に分布するため資源探査が容易であること
- 4.
- 開発時の環境汚染源として問題となるトリウム(Th)やウラン(U)などの放射性元素をほとんど含まないこと
- 5.
- 常温の希酸で容易にレアアースを抽出できること
2013年には日本の排他的経済水域内で「超高濃度レアアース泥」が発見されたほか、2014年にはインド洋においてもレアアース泥の存在が報告され(いずれも加藤教授らの研究グループによる)、レアアースの新規資源として大きな注目を集めています。
[用語3] 生物源リン酸カルシウム(BCP) : 生物の歯や骨を構成する物質であり、レアアースを非常に高い濃度(15,000 ppm以上)まで濃集しています。レアアース泥中には魚類などの歯や骨片として多く含まれています。薄い塩酸や硫酸で容易に溶かすことができ、含まれているレアアースのほぼ全量を溶液中に回収することが可能です。
![生物源リン酸カルシウム(BCP)]()
[用語4] ハイドロサイクロン : 分級装置の一種であり、液体中に懸濁する固体粒子を、遠心力を利用して沈降分離する機器(下図)。構造が極めて単純で処理能力も高いため、工業用水の浄化や金属粉・セラミック原料の分級など工業的にも広く利用されています。内部に液体を満たすため、深海の大きな水圧の下でも問題なく稼働し、原理的に分級が可能と考えられます。海底への設置が可能となれば、レアアース泥揚泥コストの大幅な削減も期待されます。
![ハイドロサイクロン]()
論文情報
掲載誌 : |
Scientific Reports |
論文タイトル : |
The tremendous potential of deep-sea mud as a source of rare-earth elements |
著者 : |
髙谷雄太郎1-4、安川和孝5,3、川崎健寛5、藤永公一郎3,2、大田隼一郎3,2,6、臼井洋一7,4、中村謙太郎5、木村純一6、常青6、浜田盛久6、ドドビバ・ジョルジ5、野崎達生2-4,8、飯島耕一4、森澤友博9、桑原拓馬10、石田泰之11、市村高央11、北詰昌樹12、藤田豊久5、加藤泰浩2-5*
|
所属 : |
1早稲田大学 創造理工学部 環境資源工学科
2東京大学大学院工学系研究科 エネルギー・資源フロンティアセンター
3千葉工業大学 次世代海洋資源研究センター
4海洋研究開発機構 海底資源研究開発センター
5東京大学大学院工学系研究科 システム創成学専攻
6海洋研究開発機構 地球内部物質循環研究分野
7海洋研究開発機構 地球深部ダイナミクス研究分野
8神戸大学大学院 理学研究科 惑星学専攻
9東亜建設工業株式会社 エンジニアリング事業部
10東亜建設工業株式会社 技術研究開発センター
11太平洋セメント株式会社 中央研究所
12東京工業大学 環境・社会理工学院 土木・環境工学系
*責任著者:加藤泰浩
|
DOI : |
|
<$mt:Include module="#G-13_環境・社会理工学院モジュール" blog_id=69 $>