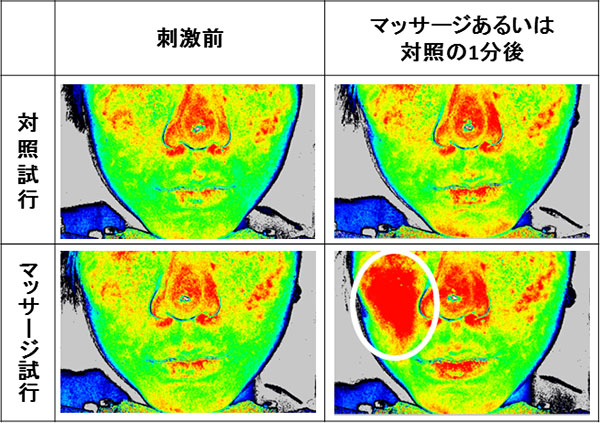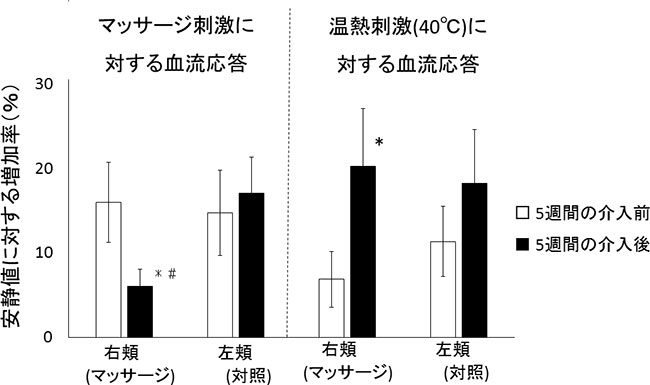指定国立大学法人構想の要となる未来社会DESIGN機構が9月に発足し、そのキックオフイベントを、10月28日に大岡山キャンパス東工大蔵前会館において開催しました。
未来社会DESIGN機構とは、予測可能な未来とはちがう「人々が望む未来社会とは何か」を、社会と一緒になって考えデザインし、導き出された未来社会像を実現するために必要な要素(技術、政策など)を含めて広く社会のみなさまと共有し、共に実現に向けた活動を行うことで社会に貢献する組織です。
本学にとっても新しい挑戦となる機構の取り組みのために、2018年春から学院やリベラルアーツ研究教育院から参加する学内構成員の他、実業家や広告会社、映像制作会社の方々など多様な学外構成員を交え、機構の在り方や目指すべき方向について議論を重ねてきました。
今回のキックオフイベントには、本学学生・教職員はもちろんのこと、学外からも高校生、社会人、卒業生など130名以上の多様な方々が参加しました。楽しく、真剣に、熱く語り合った当日の会場の盛り上がりの様子をご紹介します。
第1部 未来社会を考える共創ワークショップ 第1回「ボーダーを、超えよう。」
![司会進行する中野教授(右)と伊藤准教授(左)]()
司会進行する中野教授(右)と伊藤准教授(左)
「ボーダーを、超えよう。」というテーマは、未来社会DESIGN機構の構成員が事前の議論の中で出し合った「私の創りたい未来社会のイメージ」からキーワードを抽出して議論を進め、このテーマのもと、学内外の方々と話し合いたいという思いから設定しました。このワークショップには、本学学生及び本学教職員の他、高校生、卒業生、一般社会人の方のご参加がありました。
ワークショップではリベラルアーツ研究教育院の中野民夫教授と伊藤亜紗准教授がファシリテーター役となり、本学教員による最先端の研究に関する講演で述べられた新しい科学・技術や予測される世界の状況を踏まえて、どのような「ボーダー」を超えられるか、どのような未来社会が構想できるか、参加者が話し合いをしていきました。
話し合いに入る前のアイスブレークでは、参加者が4~5名のグループになり、自己紹介を行ったり、2030年に向けた東工大のステートメント「ちがう未来を、見つめていく」を読み上げたり、さらに中野教授がギターを持って自作の歌を全員と歌うなどして、参加者同士の距離を縮めていきました。第1部のメインであるワールドカフェ※1方式で行うワークショップでは、どちらの意見が正しいのかを競う「議論」ではなく、あるテーマについて向かい合って話し合い、新たな「発見」「創造」につなげられるよう「対話」することを目指します。対話する際のルールが中野教授から伝えられた後、丸くカットされた段ボール「えんたくん」を囲んで、ワークショップが始まりました。
![無線通信技術の発展について講演する岡田准教授]()
無線通信技術の発展について講演する岡田准教授
第1ラウンドでの話し合いのテーマとなる最先端の研究の例として、「無線通信のボーダーを超える!」と題し、工学院 電気電子系の岡田健一准教授が講演を行いました。岡田准教授は、100年後の電気通信、運輸、軍事、医療など23項目について20世紀に実現するであろう科学・技術を予言した1901年の新聞を取り上げ、当時予言された通信技術のうち、多くの技術が実現されていること、続けてこの約20年間における無線技術の急速な進歩について、講演をしました。
この講演を元に、5Gと呼ばれる次世代の通信速度が実現したら何がしたいか、グループごとに「えんたくん」を囲み円座になって対話していきました。対話ののち、ミニハーベスト(意見の共有)として2~3名の参加者が、対話から生まれた意見について参加者全員に対して発表しました。このように講演、対話、ミニハーベストを1ラウンドとして、さらに2ラウンドを同様の形式で行いました。
第2ラウンドでは、環境・社会理工学院 土木・環境工学系の鼎信次郎教授が、「変化する地球の環境-「ボーダー」を考えるために-」という題で、水、人口、地球温暖化といった観点から、変わりつつある地球環境について講演しました。最後に鼎教授は「みなさんが変わらなくても、まわりが変わっていきます」と呼び掛けて、この変わっていく地球、世界において、私達が望むことは何かを問いかけました。
![2060~2070年頃、世界の人口が100億人を突破するといった予測を説明する鼎教授]()
2060~2070年頃、世界の人口が100億人を突破するといった
予測を説明する鼎教授
![サリドマイドを例に薬の作用メカニズムの解明の重要性と、新薬の開発の可能性を説明する山口教授]()
サリドマイドを例に薬の作用メカニズムの解明の重要性と、
新薬の開発の可能性を説明する山口教授
休憩をはさんで第3ラウンドでは、生命理工学院 生命理工学系から山口雄輝教授が「創薬の壁を超えて」と題して講演を行いました。山口教授は、薬が効くメカニズムを解明する前から私たちは薬を服用していることがあるという事実や、特に低分子医薬品において新薬が生まれにくくなっている現状、高額な高分子医薬品など現在の創薬を取り巻く問題を提起したうえで、人間に対して好ましい作用も、好ましくない作用ももたらすサリドマイドの研究を中心に、薬の作用メカニズムの解明の重要性を説明しました。
第1ラウンドから第3ラウンドまで、ラウンドごとに議論する相手を変えつつ、最後のハーベスト(意見の共有)の時間では最初のグループに戻り、3つのラウンドの対話で印象的だったこと、これらを踏まえて、これから創りたい未来は何か、その思いを共有しました。
![それぞれがワークシートに描いた「私の創りたい未来」を参加者同士で共有]()
それぞれがワークシートに描いた「私の創りたい未来」を
参加者同士で共有
その後まとめとして行われたのが、ワークシートを使い、「現在の課題・心配」と「超えたいボーダー」を挙げたうえで、「私の創りたい未来」を、絵と言葉で参加者それぞれが描くことでした。それまでのにぎやかな対話とは対照的に会場はしばし静まり返り、それぞれが集中してワークシートに取組みました。描き終わった人はワークシートをもって、他の参加者とお互いのアイデアを共有し、さらに、講演やミニハーベストで共有された意見を記録してきたグラフィックレコーディングを用いて、ワークショップ全体の振り返りを全員で行いました。
その後、一度グループに戻り、お互いの「創りたい未来」を共有して感想を述べたのち、全員が会場内で大きな円を作りました。ここで、中野教授から「何かやりたくなったことがある人、手を挙げて!」と呼びかけると、数名の学生から手が上がり、「学生の団体を作りたい」「東工大生が名刺を持ったらいい」「小さなコミュニティをつなげるようなことをしたい」「異なる価値を共有して認識するため、場を作ってみんなと語り合いたい」といった意見が出されました。
![グラフィックレコーディングを囲み、参加者全員による今日の議論の振り返り]()
グラフィックレコーディングを囲み、
参加者全員による今日の議論の振り返り
![「何かやりたくなったことがある人!」と中野教授の呼びかけに、すぐに手を挙げた学生も]()
「何かやりたくなったことがある人!」と中野教授の呼びかけに、
すぐに手を挙げた学生も
最後に、中野教授から一本締めならぬ「一本ジャンプ」の提案があり、参加者を代表して高校3年生の女子生徒が「自分のボーダーを超えられた」という感想を述べた後に、彼女の掛け声にあわせて全員が目の前のボーダーを超えるイメージでジャンプしました。
※1 ワールドカフェ
1995年にアメリカのアニータ・ブラウン氏とディビッド・アイザックス氏によって開発・提唱された話し合いの方法。カフェのようにリラックスした雰囲気の場を作り、全体を4~6名ぐらいのグループに分けてそれぞれテーブルを囲み、多様な意見を受け入れることを目的とした対話をします。(川島直、中野民夫著『えんたくん革命』、みくに出版、p64から抜粋)
※2 グラフィックレコーディング
会議の中で人々の議論をリアルタイムでグラフィックに可視化する手段。グラフィックレコーディングを行うグラフィックレコーダーは人々の対話や議論の内容を聞き分け整理しながら、リアルタイムでグラフィックに変換し、可視化していきます(清水淳子著『Graphic Recorder ― 議論を可視化するグラフィックレコーディングの教科書』、ピー・エヌ・エヌ新社、p4及びp12から抜粋)。今回のワークショップではグラフィックレコーディングに関する書籍も出している清水淳子さんがグラフィックレコーダーを務めました。
第2部 東工大コミットメント2018 と未来社会DESIGN 機構の紹介
第2部ではワークショップ参加者以外の学内外関係者も招いて、最初に益一哉学長から、今後の大学の活動の基本的な考え方となる「東工大コミットメント2018」の発表がありました。
![東工大コミットメント2018に込めた思いを語る益学長]()
東工大コミットメント2018に込めた思いを語る益学長
これは、今年4月に就任した益学長が、学内教職員の声を聞いてつくったものです。益学長は、本学の先進的な改革をさらに進め、特に教育と研究で成果を生み出すべく共通の価値観の醸成を目指して、「多様性と寛容」「協調と挑戦」「決断と実行」という3つのコミットメントを発信するに至った思いを、ワークショップで高校生や本学学生と話した際にも、これらの考え方の重要性を感じたという話を交え、語りました。
益学長は最後に、「ボーダーを、超えよう。」というワークショップのテーマに絡めて、「一歩ボーダーを超える、今日何を超えたか、を感じ取ってほしい。未来を見つけましょう」と呼びかけました。
![未来社会DESIGN機構に注目しつづけていただくよう呼びかける佐藤機構長]()
未来社会DESIGN機構に注目しつづけていただくよう呼びかける
佐藤機構長
続けて未来社会DESIGN佐藤勲機構長から、未来社会DESIGN機構の組織概要に関する説明がありました。佐藤機構長は、こうある「べき」という未来社会像より、社会のみなさんと一緒に、こうあり「たい」という未来社会像を考えていきたい、そのためには本学だけでなく社会の色々な方々に機構の活動に注目して、今日のワークショップのように積極的に参加していただきたいと訴えました。
最後に未来社会DESIGN機構構成員でもある上田紀行リベラルアーツ研究教育院長が、「共創ワークショップから未来へ」と題して、当日参加していた未来社会 DESIGN機構の学外構成員を紹介するとともに壇上にお呼びし、第1部の共創ワークショップで感じたことや、これから機構でやっていきたいこと、さらにそれぞれのこだわりや未来に対する原動力について、一人ひとり聞いていきました。
![登壇者による座談会の様子(左から、上田教授、株式会社ロフトワークの林 千晶氏、株式会社博報堂の根本かおり氏、科学技術振興機構 研究開発戦略センターの倉持隆雄氏、株式会社円谷プロダクションの杢野純子氏)]()
登壇者による座談会の様子
(左から、上田教授、株式会社ロフトワークの林 千晶氏、株式会社博報堂の根本かおり氏、科学技術振興機構 研究開発戦略センターの倉持隆雄氏、株式会社円谷プロダクションの杢野純子氏)
登壇者からは、決まったシナリオがないところで自由に議論ができる雰囲気や本日のこういう場を大事にしていきたいといった意見や、もっと多くの若い人たちの率直な意見を取り入れていってほしいといった感想が出されました。
第2部の後は、会場を百年記念館に移して、懇親会を開催しました。この場でも、いくつもの小グループが形成され、第1部の対話の続きや今後への期待を語り合う姿が見られました。
イベント終了の翌日から11月2日まで、第1部の共創ワークショップで参加者が描いた「私の創りたい未来」と、講演や議論を記録したグラフィックレコーディングを百年記念館に展示し、今回参加できなかった方へも未来社会DESIGN機構の取り組みを紹介しました。
![未来社会DESIGN機構キックオフイベントのちらし(左)と、「ボーダー」を意識した百年記念館の装飾(右)]()
![未来社会DESIGN機構キックオフイベントのちらし(左)と、「ボーダー」を意識した百年記念館の装飾(右)]()
未来社会DESIGN機構キックオフイベントのちらし(左)と、「ボーダー」を意識した百年記念館の装飾(右)
未来社会DESIGN機構では、変わりゆく時代のなかで、今回のワークショップのように、自由に、ありたい社会を語り合い構想する仕組みを作りつつ、今後、参加者が描いた「私の創りたい未来」をもとに、「こうありたい」という未来社会像を描いていきます。
<$mt:Include module="#G-28_TokyoTech2030モジュール" blog_id=69 $>